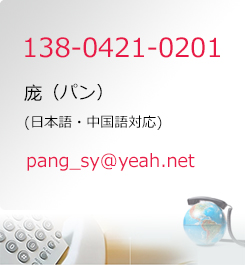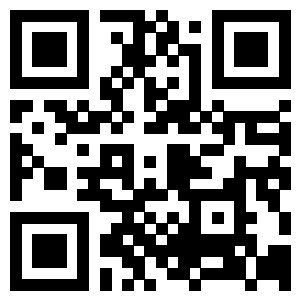ヤマダ電機が中国で受け入れらず撤退に至った理由
by呉 明憲 on 2013/5/16
まだまだ「サービスよりも価格重視」だった中国家電量販業界
ヤマダ電機は中国に瀋陽、天津、南京の順番で3店舗出店していましたが、4月22日付のプレスリリースで昨年3月22日にオープンしたばかりの南京店を5月31日を以って閉店することを発表しました。中国市場進出当初3年間で5店舗、つまり半年ごとに1店舗オープンし、3年後には年商1,000億円を目指すとしていましたが、結局のところ出店は3店舗にとどまっており、なおかつ南京店を閉鎖することになってしまったわけです。
店舗閉鎖の理由としては、「中国国内における家電市場環境の変化に加え、サプライチェーン(商流・物流)の構築が十分にできなかったことによる販売不振等」を挙げています。
中国ではベストバイ(中国ブランドの五星電器は営業中)、 メディアマルクト(独メトロとフォックスコン(鴻海)の合弁)といった外資家電量販大手が相次いで撤退しており、メディアマルクトが中国の全店舗を閉店することを表明した時点でヤマダ電機は南京市場から撤退することを検討し始めていたようです。また、他の家電量販店同様中国から完全撤退する計画があるという情報がありますが、これはあくまで未確認情報であります。
ヤマダ電機は中国の家電量販メガプレーヤーの蘇寧、国美を相手に差別化を図ろうと勝負したのですが、その差別化とは、(1) 商品買取式、(2) 会員制、の二つです。

この2つはいずれも中国にはあまり見られない形態ですが、中国では規模と価格が決定的な要素で、それ以外は議論するに値しないという人がいるくらい価格に対して敏感であります。「価格も大事だが、サービスを付加価値として提供することは受け入れられるはずだ」という考え方はサービス業でよく見られ、その考え方はわかりますし、実際にそれがうまくいっている事例もあろうかと思います。
しかし残念ながら家電量販はまだまだ価格というものが最も重視されるのが現状であるといえそうです。外資の場合は後発組なので当然小さい規模からスタートするのですが、小さいがゆえ購入量が少なく、サプライヤーに対する価格競争力も弱いという問題があります。
また、商品買取式は販売価格の主導権を取ることはできるのですが、サプライヤーに店舗賃料や内装等の費用を転嫁することができないうえに、自腹で購買員を雇用し、店員を雇用し、商品ロス等をかぶり、要するに小売商(店舗側)が多くのリスクを抱える形になっています。
一方で、中国の家電量販店は、出店コストをサプライヤーに付け替えたりすることでコストをおさえ、蘇寧や国美は短期間の間で全国展開することができています。
結局のところ規模の違い、そしてそれに伴う購買コストの違い(小売価格に転嫁)から、価格競争力で負ける、あるいは薄利に終わってしまうのが今までの外資家電量販店の負けパターンといえそうです。
「価格に転嫁されるなら、そのサービスはいらない」
では、消費者目線で見た場合、蘇寧や国美の店舗というのはどれだけ魅力があるのでしょうか。個人的な考え方を申し上げますと、多くの店舗があるのでちょっと必要と思った時には気軽に行けるというのがあります。店員の応対はそれほど期待していません。サービスが良いに越したことはないですが、サービスの概念がまだまだ薄い中国であまりサービスに期待し過ぎるとかえってストレスがたまってしまうだけです。
「サービスが良くて価格が高くなるのならサービスが悪くても価格が安い方が良い」という人の方が大多数でしょう。まして中国ではサービスを受け慣れていない人がまだまだ多いので、サービスというのは差別化要因にはなりえますが、価格に転嫁されているようであれば「やっぱりそのサービスいらない」と思う人が多いと思います。
それと、決め打ちで買う場合、例えばこのデジカメが欲しい、あの電子レンジが欲しいということであれば、わざわざ出かけて買いに行かず、ネットショッピングで購入することを選択する人も少なくありません。実際に私も電子レンジや掃除機をネットで購入しました。
外資の成功事例に続け!「合弁」で販路開拓も選択肢に
こんなことを並べていくと新たに家電量販に参入しない方が良いという結論になってしまいますが、それはそれで悔しい話です。ひょっとして小売りという業態が難しいのでしょうか、それとも家電量販という形態が難しいのでしょうか。ひょっとするとまだデパートの方がいいのでしょうか。
中国の消費者もデパートよりもショッピングモールを好むようになってきていると言われていることを考えるとデパートもちょっとリスキーかもしれないですが、外資でも頑張っているところはあります。
上海で言えば香港系の久光百貨店。上海で単一店舗で第三位の売り上げを上げています。スーパーは外資でも成功しているところがあります。外資スーパーの売り上げトップは台湾系の大潤発、日系ではイトーヨーカ堂がよく成功事例として取り上げられます。こうしてみますと成功事例のない家電量販という業界が難しいのかもしれません。
考えられる方法の一つとしては「合弁」で入っていくことでしょうか。
最近合弁も悪くないと思うようになってきています。よく合弁の場合清算するのが大変だといいます。一方で独資で進出した場合販路開拓に苦労してなかなか思い通りの業績を上げられていない企業もあります。こうなると、清算するときは大変かもしれないけど販路開拓では頼りになる合弁という形態か、清算は簡単だけども販路開拓は大変という独資という形態か、このどちらをとるのかという構図になってくるのではないかと思います。
清算が大変、販路開拓が大変、どっちのリスクを取るかですね。ターゲットをどこに置くか、あるいはどのようなビジネスモデルにするのかにより左右されるとは思いますが、個人的には合弁という形態はもっと見直されてもいいのではないかと思っています。