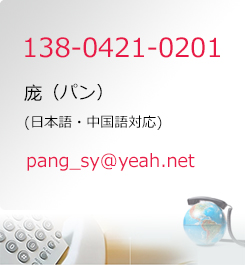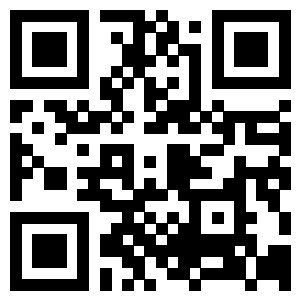中国人に絶対に贈ってはいけない品物(ケーススタディ「贈る物選びには要注意-その1」)
中国出張のとき、取引先の担当者にお土産を買って行こうと思います。相手は仕事で日頃からお世話になっている中国人です。しかし、この中に「贈り物」には相応しくない品物があります。①から⑥の品物が「贈り物」として相応しくないと思うものには×、問題ないと思うものには○をつけてください。中には中国人に贈ってしまうとたいへん失礼になる絶対に贈ってはいけない品物があります。
① 職人が手作りで仕上げた伝統工芸品の和傘
② 日本各地の有名お菓子を集めた詰め合わせセット
③ 設立25周年を記念して作ったインテリアとしても美しい木目調の置時計
④ 秋葉原でしか買えない数量限定のキャラクターデザインの可愛い扇子
⑤ 太陽パネルで電池交換の不要なハイテク目覚まし時計
⑥ 会社のエコキャンペーンで製作し、TVでも有名になった緑の帽子
ここで解答を読み進める前に、1分間程、時間を作り、自分で○か×か考えてみてください。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
【解答】
詳しい解説の前に、先に「解答」(結論)を述べましょう。答えは①× ②× ③× ③× ④× ⑤× ⑥×です。つまり、これらの品物はすべて「贈り物」としては相応しくないものです。②のお菓子の詰め合わせセットは、品物がダメなのではなく、渡すときの言葉に要注意です。後で詳しく解説します。
まず、絶対に贈ってはいけない品物、それは「時計」です。③の置時計、それから⑤の目覚まし時計も贈ってはいけない品物です。中国では「時計」を贈ることは厳禁。贈り物として中国人に絶対にプレゼントしてはいけない品物です。それは中国語の発音と関係があります。「時計」は中国語で「鐘」(zhong)と発音します。置時計は「坐鐘」(zuozhong)、目覚まし時計は「閙鐘」(naozhong)です。「時計」の「鐘」(zhong)という発音が、「終」(zhong)と発音と同じです。「時計」を送るということは、「終了」、「おしまい」を連想させます。つまり、「私たちの関係をこれで終わりにしましょう」という意味に通じます。言い換えると「絶縁状」を叩きつける「絶交宣言」なのです。
また、「時計を送る」という意味の「送鐘」(songzhong)という言葉は、同じ発音で「送終」(songzhong)という言葉を連想させ、これは「死に水を取る」、「死者を送る」という意味です。縁起が悪いことを連想させる言葉なのです。選択肢には「会社設立25周年記念」とか、「木目調の美しい」とか、「太陽光発電」とか、「ハイテク」の時計とありますが、実はこれらはあまり問題ではありません。会社のノベルティグッツでも、品物がどんなにりっぱでも、希少価値のあるものでも「時計」は贈ってはいけない品物です。
発音の音繋がりで①の「傘」や④の「扇子」も避けたほうがいい品物です。中国語の発音では「雨傘」(yusan)、「扇子」(shanzi)と言います。これらの言葉は、中国語の「解散」(jiesan)、「離散」(lisan)の「散」(san)という言葉を連想させます。つまり、「散らばる」、「ばらばらになる」、「別れ別れになる」という意味。「関係が壊れる」、「縁が遠のく」というマイナスイメージを連想させる言葉なのです。日本でも結婚式では「終わり」と言わずに「お開き」と言ったり、「終わる」や「分かれる」といった言葉を使わないように注意を払います。「時計」「傘」「扇子」などは贈り物としては相応しくない品物なのです。
ある企業の社員研修でこの話をしたところ、中国業務の担当者が青い顔をして「あと2週間早くその話を聞きたかった」という方がいらっしゃいました。そうです。贈っちゃったんですね。彼は、「そう言えば相手は何か怪訝な顔をしていた」と言います。それはもっともです。もし、身内の結婚式で招待者のひとりが「黒いネクタイ」をして来たとしたら、皆さんはどう思いますか?きっとびっくりして、「縁起でもない」と思うはずです。「時計」をプレゼントされる中国人は、それと同じような感覚を持ったはずです。
「私は取引先が事務所を開設するときにお祝いに『掛け時計』を送りました」という方もいらっしゃいました。ついついやってしまいがちですが、これもNGです。掛け時計は「掛鐘」(guazhong)と言います。「鐘」(zhong)の文字が使われているのでダメですね。
「腕時計はいいんでしょうか?」という質問もよくあります。「腕時計」は中国語では「手表」(shoubiao)と言います。「鐘」(zhong)という文字を使わないため、基本的には「腕時計」は問題ありません。しかし、「あまり積極的に選ぶべき品物じゃないですね」という中国人の友人jからのアドバイス。もっとよい別な品物があればそちらを選んだほうがいいでしょう。
2週間前に時計を贈ってしまった彼は、「どうしたらいいでしょうか?」と真剣な表情です。もし、「時計を贈ってはいけない」ということを知っていれば、贈らなかったはずです。「知らない」というだけでつい犯してしまう典型的なコミュニケーションギャップの事例です。知ってさえいれば、犯さなかったコミュニケーション上のミスです。
このように中国では「知らない」というだけで生まれるコミュニケーションギャップがけっこうたくさんあります。このコラムではこうした習慣の違いや考え方の違いにスポットを当て、中国人とうまくつきあっていくためにはどうしたらいいいか、日本人が知っておきたいポイントを取り上げ、解説していきたいと思います。日本人には理解しにくい考え方や彼らの行動、そしてその背景にある中国人の価値観をできるだけ身近な事柄を取り上げながらわかりやすく解説していきます。
「緑の帽子」と「お菓子の詰め合わせ」の解説は次回のコラムにて・・・